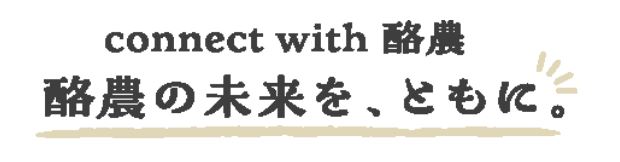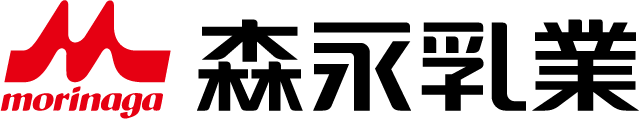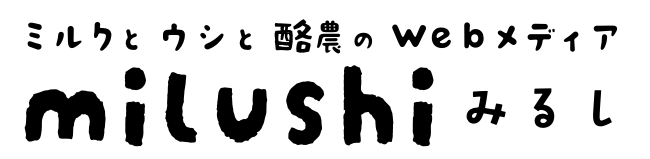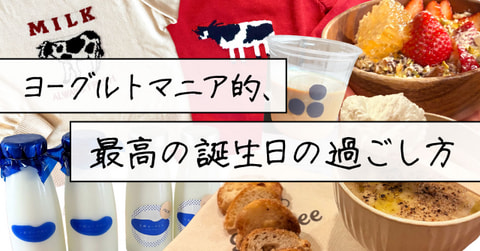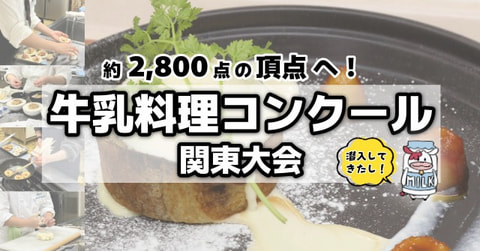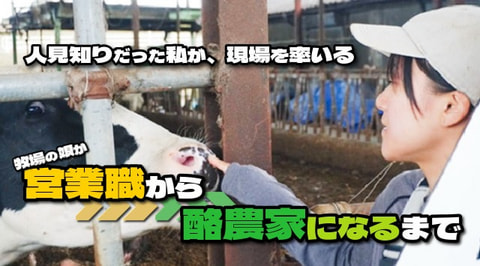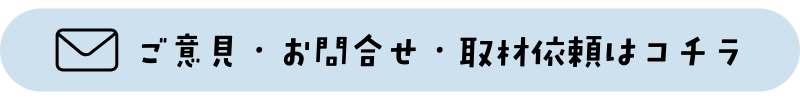ニュージーランドへ酪農視察に行ってきました!

2025年9月、ニュージーランドの酪農を勉強しに行ってきました。
ニュージーランド(NZ)の人口は約530万人ですが、乳牛頭数も約500万頭。
ちなみに肉牛頭数は約350万頭、ヒツジは約2,300万頭。
人より牛の方が多いだけでなく、ヒツジは牛のさらに2.7倍いるのでやっぱりヒツジの国なのかも。
ニュージーランドは放牧大国
車で移動しましたが、主要な都市を除けば国内のほとんどが放牧草地って感じ。

南島は平坦で広い草地が広がっていました。
北海道の道東の根釧地区や十勝地区な感じ。
あまり大きな川がないため灌漑(かんがい)設備※が整備され、企業的に酪農がされているようでした。
※灌漑(かんがい)設備:農作物を育てるために人工的に水を供給する設備のこと


一方の北島は山がちで、こちらは北海道のオホーツク地方である、常呂郡(ところぐん)置戸町(おけとちょう)・訓子府町(くんねっぷちょう)や、宗谷地方な感じ。
害獣が少ないので、南北とも囲いは非常に簡単な電牧※だけが多かったです。(雨であまりいい写真が取れず…)
※電牧:電気牧柵(でんきぼくさく)の略で、電気を通した柵を使って牛などの家畜が囲いの外に出ないようにする仕組み
ニュージーランドの牛たち
牛たちにも会ってきました。
放牧主体なので、人と接するのは搾乳(さくにゅう※)時にミルキングパーラー※に来た時くらい。
※搾乳(さくにゅう):牛などのほ乳類からミルクをしぼること
※ミルキングパーラー:牛のミルクをしぼるための専用設備。建屋のなかにミルクをしぼる専用エリアを設け、牛がそこに入っていき定位置におさまると、作業をする人がミルクをしぼる機械(ミルカー)を取り付けます。
なので、日本の牛たちに比べると、とってもシャイな感じの子たちが多かったです。
手を差し伸べると、みんなおずおずと数歩下がり、そこから寄ってこない。
日本だと、最初は少し下がるけど、そのうち興味深げに近寄ってくるので、ずいぶん違うように感じました(みんな緊張していて、しっぽ左振りが多く、あんまり「会話」はできなかったのは残念…)。
★「しっぽの法則」の記事👉『【牛フリーク道】牛と人生(牛生?)相談したいんです』はこちらから


ニュージーランドの牛たちはホルスタイン種(現地では「フリージアン」と呼ぶのが主流。たくさんミルクが生産できるように改良されてきた種類)とジャージー種(脂肪分が高く、濃厚なミルクを生産するように改良されてきた種類)の混血牛群が主。
これは生乳の取引が乳量ではなく、固形分取引のため、できるだけ濃い目の生乳を生産したいということからです。
ジャージーの特徴でもあるくりくりした瞳を持ったホルさんって感じの子や、微妙に茶色がかった白黒(白茶?)柄とか、同じ牛群でも見た目は様々です。
体高は140センチくらいで、かなり小さいなあと感じます。
ニュージーランドの生乳と生乳取引
それでも1乳期で1頭当たり5~6千㎏生産するそうで、それ以上に乳脂肪分は4.7~4.8%、乳たんぱく質も3.6%程度ととても濃い乳を生産しています。
日本の牛乳は、「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年12月27日厚生省令第52号、令和6年4月題名改正)」により、生乳100%、成分無調整で殺菌したもの、乳脂肪分3.0%以上、無脂乳固形分8.0%以上の条件を満たさないと「牛乳」として販売することができません。
例えば「森永牛乳」は、乳脂肪分3.5%以上、無脂乳固形分8.3%以上です。
また、日本の生乳の乳たんぱく質については、農林水産省の「家畜改良増殖目標」によると、乳用雌牛の能力に関する表型値目標数値(ホルスタイン種全国平均)は、2025年度(令和7年度)時点で3.28%です。
なお、日本では、北海道酪農検定検査協会による生乳検査結果では、2024年度実績で、乳脂肪率4.099%、乳たんぱく質率3.393%となっています。

ニュージーランドの生乳取引は「乳固形分」取引となっていますが、この時の乳固形分は「乳脂肪分+乳たんぱく質分」であり、乳糖やミネラルはノーカウント(日本でいう『無脂乳固形分』はこれらも含まれます)。
ちょうど訪問したころ(9月下旬)に今シーズンの乳価が発表されていました。
乳固形分1㎏あたり約10NZドル。日本円にすると約900円。
乳脂肪分+乳たんぱく質分=約8.3%となりますので、
日本式に計算すると900円✕8.3%=約75円/生乳1㎏となります。
日本の半分より少し高いくらい。
それでも10ドルという水準は歴史的に高いそうで、酪農家さんたちの生産モチベーションは相当上がっているようでした。
実際、訪問した酪農家さん(Omaka Farms)も「今は搾れば搾るだけ儲かる!」と嬉しそうでした。
飼料は放牧主体で、搾乳時に少量の濃厚飼料※を与える程度、500頭の規模で従事者は経営者入れて5人くらいと集約的でもあるので、非常に低コストでの生産ができているようでした。
※濃厚飼料:牛がたくさんのミルクを出すために必要な栄養(エネルギーやたんぱく質)を効率よく補うための、穀物などを中心とした高栄養な飼料のこと。
ニュージーランドの放牧管理にみるDX進化

訪問した農場は500頭を350haの草地で飼養していました。
最近は放牧管理にもDXが進んでいて、牛の首にトランスポンダーをつけて、牛のいる位置をGPSで管理しています。
さらに草地も電牧で区切らずに、ソフトウェアの画面上で擬似柵(バーチャル・フェンス)を線引きすることで、牛をそのエリア内に誘導することができるようで、搾乳を終えた牛たちは、それぞれ決められた牧区へ自発的に歩いていました。
すげー!とやたらと感動していました。
搾乳後、牧区へ帰る牛たち
ニュージーランドの酪農は世界でもトップクラスの放牧酪農です。
農場長は牛群管理よりも草地管理を中心に行っている様子がうかがえました。
より良い草地の育成や草の成長、放牧地サイクルなどを中心に管理して、そのうえでどれだけ放牧圧※をかけるかという感じで、土地単位面積当たりの乳固形分をいかに得るかが経営の基本ということでした。
※放牧圧:牧草地の面積に対して放牧する牛の頭数の割合。1ヘクタールあたりに何頭の牛を放しているかを表すもので、牛の密度が高いほど「放牧圧が高い」、低いほど「放牧圧が低い」。
牛というより土地起点ということですね。

おわりに
9月下旬は春先にあたり、少し肌寒い感じがありましたが、出会う方々は皆さんフレンドリーに接していただき、豊かな国民性をうかがうことができました。
後ろ髪を思いっきり引かれながら、まだ暑い9月の日本に帰国しました。
また行きたいなぁ…。